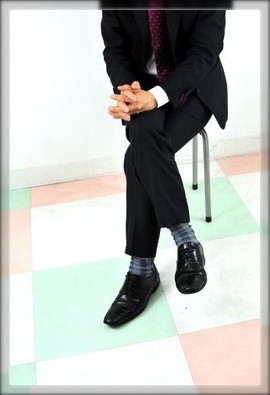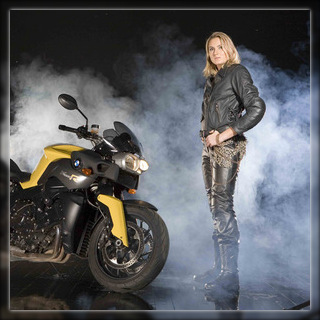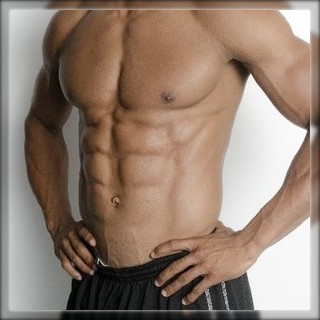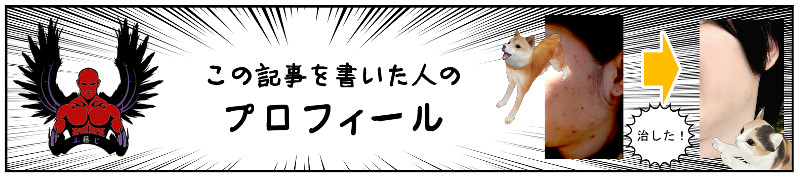自分の子供がサッカーを始めた時に今のうちから教えておくべきことは何なのか。
また、これから子供を指導するコーチや監督は何を教えるべきなのか。
私自身小学一年生からサッカーを始めずっとキャプテンを務め、大人になってからは地域の小学生サッカーチームの監督していた経験があります。
昔から今まで私が変わってないと言えるもの。それはサッカーが大好きだという気持ちです。
今でもいつでもサッカーができるように体を鍛えていますし、三日に一回はサッカーの夢を見ます(子供時代のユニフォーム忘れる悪夢多し)。
今回はそんな私が、小学生をこんな風に指導したらみんなえげつない程成長したよ!という記事になります。
指導は哲学なのでやり方はそれぞれあっていいし、私のやり方が間違っていると思う方もいるでしょう。
でも引き出しは多いほうが良いというのは間違いないので、ぜひあったか~い目で読んでくださいませ。
長くなるので今回は子供本来の力を引き出す方法です。
仲間のせいにしないという思いやり
最初に小学生にチームプレーとは何ぞや?という部分で理解を深めてもらう方法です。
物事には必ず原因と結果があります。
当たり前の話です。
しかしサッカーにおいては個人スポーツと違い結果の原因がわかりづらく、複雑です。
試合に負けた時に子供は、相手に抜かれたDF、セービングミスしたキーパー、シュートを外したFWなど目に見えるわかりやすい原因を責めたくなります。
それこそ小学生だと余計に大人になれない感情をぶつけてしまいがちです。
このような気持ちそれ自体を責める人も多いですが、私は当然の思考だと思います。悔しい気持ちは本気でやっているからこそですよ(もちろんそれを態度に出した時点でOUTですが)。
そこで私の指導方法は結果に対して必ず一人ひとりに責任があること、そしてその重さは平等であることを子供たちに理解してもらいます。
高校生くらいになれば個人的に呼び出して指導するのは当たり前ですが、小学生の場合は結果に対して悪者を一人つくるのはナンセンスだと思うからです。
失敗したのは本人が一番わかっているし、責任を子供ながらにしっかり感じています。
それを必要以上に周りの子供、ましてや指導する大人が責めたててしまうと次回以降のプレーが萎縮してしまい、のびのびできません。
負けたときはみんなの責任=勝ったときはみんなの喜び
これを徹底して教え込みます。
具体的な指導方法です。
子供たちにシュートを決められたときの映像を見せ、その前のパス、その前の前のパス…とプレーを遡っていき、味方チーム全員が失点に関与してることを確認させます。
すると、「あの時に自分がボールを奪えていたらあの失点は無かったのか」と映像から理解できます。
一瞬でも一回でもサボったら失点につながる。たまたま最後のプレーの近くにいた仲間が悪者みたくなっただけだった。ということをしっかり考えさせて理解させます。
この映像検証をやった結果、
・まずチーム全員がサボらなくなった=運動量が上がりボール支配率があがった
・見方を罵る行為が無くなった→自然にドンマイの声が増えた
・チームとして機能するようになった
チームプレーは上から「仲間を思いやりなさい!」と怒鳴ったところで中々根付きません。
小学生相手でもしっかり結果に責任をそれぞれ負わせ、味方を自然に思いやれる環境をつくることが大切です。
注意点)あまり上手くない子はミスの回数が多いです。逆に上手い子はあまりミスをしません。
もし遡って誰かのミスが多ければ編集したり、失点を遡るのではなく得点を遡りましょう。
結果に対して全員が責任があることを理解させることが目的ですので、チームの状況と照らし合わせて臨機応変に対応してください。
私はチームの状況が良くなってからはポジティブな内容を多くしました。
子供に考えさせることが何より大切

指導者さんに訊きます。漠然と「次はシュート練習やるよー」「次はパス回しするよー」となっていませんか。
私の小学生時代もそうでした。コーチから言われるメニューを淡々とこなす練習ばかり。
しかし子供ながらに「この練習何の意味があるんだよ」と思うメニューもありました。
これ…
はっきり言ってしまうと子供が目的がわかっていない練習は無駄です。
何時間やっても成果は出ません。
子供は馬鹿じゃありません。しっかり考え物事の本質を見極めようとしています。
なにより大切なのは子供にこの練習をすれば勝てる!上手くなる!と理解してもらうことです。
私は新しい練習をする時に必ず子供たちに質問しながら説明していきます。
シュート練習の場合の子供たちとのやり取りを例にします。
私)サッカーで試合に勝つ為にはどうしたらいいのかな?
子)相手より多く点を取る
私)より点を多く取る為にはどうしたらいいのかな?
子)シュートを決める
私)シュートを上手く決めるためにはどうしたいいのかな?
子)シュート練習をする
私)今までだってシュート練習はしてきたぞ?もっとシュートが上手くなる為にはどうしたらいいかな?
子)…
私)大丈夫、焦らないでゆっくり考えてみよう
子)相手(DF)がいない時といるときだと違う
子)練習だとただなんとなくやってしまう
子)本番にはあんな良いパスはこない
私)なるほどなるほど…
そうしたら今の案をまとめて練習メニューを決めよう。
パスの出し手と受け手にそれぞれ一人ずつDFをつける。DFは少し離れたところからスタート。受け手はどんな形でも良いからシュートを決める。DFはそれを死に物狂いで止める。
だらだらやっても身に付かないからそれぞれシュート5回、パス5回、DF5回やってまた集合。
練習後
私)この方法でシュートが前より上手くなると思うかい?
子)前の練習方法よりはいい…かも?
私)よし!そしたらしばらくパスの出し手の位置を変更しながらこの練習を続けてみよう!
子)はい!
だいぶ端折りましたけど小学生高学年だとこんな感じです。
いちいち手間がかかる!と思ってもこのやり取りするのは最初だけです。一度子供たちが納得すればあとは流れでできます。
大切なのは子供たちが自分で考えること。そして現状に疑問を持ち続けること。
指導者はその発想や考えを最大限尊重すべきです。
自分のチームを作ろうとするのは大いに結構ですが、上から押さえつけて子供が本来持っている自由な発想や伸びシロを潰してしまっては本末転倒です。
そしてこのシュート練習をやっていくとパスの出し手の精度や最初のトラップの精度が大切なのが子供ながらにわかってきます。
そこでパスの練習やトラップの練習をしていくと実践を想定した動きができます。
「なぜこんなつまらないパスやトラップの練習ばかりやらされるのだろう…」
から
「このパスやトラップが上手くなればシュートが決まる!」
という思考になり、つまらない練習も少しだけ飽きずに面白くできることでしょう。
このときに「後でやるシュート練習を想定しろよー♪」と声をかければよりわかりやすいですね。
次の記事では、小学生の頃に絶対やるべき練習方法をご紹介します。